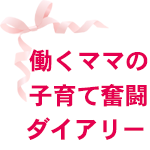避難情報について
大津波や台風などによる水害、そして土砂災害などが発生したとき、各市町村から避難指示が発令されます。
私たちはそれらを避難情報として受け取り、自分たちが避難するべきかどうかの判断を行います。
一口に避難情報といても、災害のレベルに応じた段階が決められており、正しく非難行動をとるためには、避難情報の名称によって瞬時に状況を判断する力が必要となります。
近年、地震や集中豪雨などによって大きな被害が発生しています。
今は無関係なところに住んでいたとしても、いつ自分自身の身に降りかかるかわかりません。
家族の命を守るためにも、きちんとした知識を身につけておくべきといえるでしょう。
まず1つ目は避難指示ですが、この指示が出されたときは、避難していない人は直ちに避難することが求められます。
基本的にはその場から立ち去る、立ち退き避難が望ましいとされていますが、移動する時間の確保が難しい場合は2階や高層階への移動などの屋内安全確保も有効とされています。
2つ目は高齢者等避難で、この情報は避難に時間がかかる身体障碍者や高齢者の方から避難を行うように促す指示のことです。
この避難指示に該当しない方も警戒することが求められ、洪水の恐れがある場合、低地や川の周辺に住んでいる方は自主的な避難が求められる状況を示しています。
そして3つ目が緊急安全確保で、この避難指示が1番重要度が高いものとなります。
すでに災害が発生している状態で、一刻も早く身の安全が確保できるような場所に移動することが求められます。
この避難情報が出るころには、状況はかなり悪化していることが予想されますので、もっと前の段階の避難指示の時にきちんと避難しておくことが求められます。
避難する場所について
避難場所に関しては、各市町村があらかじめ災害時の避難場所を地域別に定めています。
ホームページや配布されたパンフレットなどを確認して、自分たちが住んでいる地域の住人がどこに避難するべきなのかを確認しておくことが大切です。
災害の発生時に、生命の安全確保尾のために避難する場所のことを指定緊急避難場所といいます。
洪水や地震、土砂災害など災害の種類ごとに場所が指定されているので、すべての災害を想定して確認しておくことが大切です。
また、避難した住民が災害の危険がなくなるまで滞在する場所のことを指定避難所といいます。
ここでは長期的に大人数で滞在することになるので、思いやりの気持ちとマナーが大切になってきます。
そのほかにも、介護が必要な障害者や高齢者の方がご家族の中にいる場合は、二次避難所として福祉避難所というものがあります。
一般の指定避難所とあわせて、そうした選択肢もあるということを覚えておきましょう。