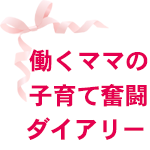今時の子どもの平均体重
幼稚園や小学校では、定期的に身体計測を行います。
この計測には、成長曲線に当てはめて発育度合いを調べる意味も含まれていることを覚えておくと良いでしょう。
成長を喜ぶとともに、成長ホルモンなどの兼ね合いから低身長などの成長障害を見極めることもできます。
学校保健統計調査で示されている令和3年度の小学校1年生相当(6歳児)の平均体重は、男児21.7キロ、女児21.2キロです。
平成元年から平均体重の推移を見ると、200グラム程多くなっている結果が出ています。
30年前と比較して、食事の質が良くなっていることなどが考えられます。
また、コロナ禍のさなかで外出などがままならず、運動不足が指摘されていた時期にも重なります。
令和3年度と平成元年度の平均身長はほぼ変わりありませんので、しばらくの間は少々ふっくら感がある子どもたちが多くなると受け止めることができます。
6歳の平均身長とされる115cmの子どもの標準体重は、29キロです。
平均体重と照らし合わせると、標準的な体型よりも多くの子がやや痩せ気味ということができるでしょう。
視点を変えると、我が子は平均的な体重なのか、標準的な体重なのかを見極めることができますよ。
太りすぎ・痩せすぎと診断されたら
小学校の身体計測では、肥満度に関する記載も行われています。
計算式に当てはめて求められ、肥満度マイナス20%~プラス20%が標準とされています。
軽度肥満はプラス30%未満、高度肥満となるとプラス50%以上の数値が示されます。
小学生の身長に対して、痩せすぎ、太り過ぎの診断が出た場合は、健康状態が懸念される状況だと言っても過言ではありません。
子ども自身の心身の健康状態が悪化している、もしくは親の虐待などが心配されることもあります。
学校で指摘を受けた場合は、小児科で相談をするとよいでしょう。
成長に関わる病気の有無を調べることができますし、子ども自身の精神状態なども診てもらえます。
ネグレクトやあまやかしなど、親子関係なども体重増加や痩せすぎに関わってきます。
ただし、体重変化を気にしすぎて親が「食べなさい」「痩せなさい」というのはできるだけ避けましょう。
その言葉が子どもに取って呪文のように響き、悪循環を招く可能性もありますよ。
太っているから食事制限、痩せているから栄養食というような無理な食生活の改善や、苦手意識を持つ運動を取り入れても子どもの負担になるだけです。
栄養バランスの乱れや「痩せなきゃ」といった暗示は、摂食障害を招く引き金にも繋がります。
まずは、適切な睡眠時間と食事の確保など、規則正しい生活を送ることを心がけましょう。
そのなかで、子どもとのびのび散歩に出かけることや、食事量を決めてゆっくり時間を掛けて食べるというような試みを取り入れて行きましょう。
医療をはじめとした第三者の力を借りることもおすすめですので、時間を掛けて取り組んでみてくださいね。