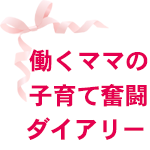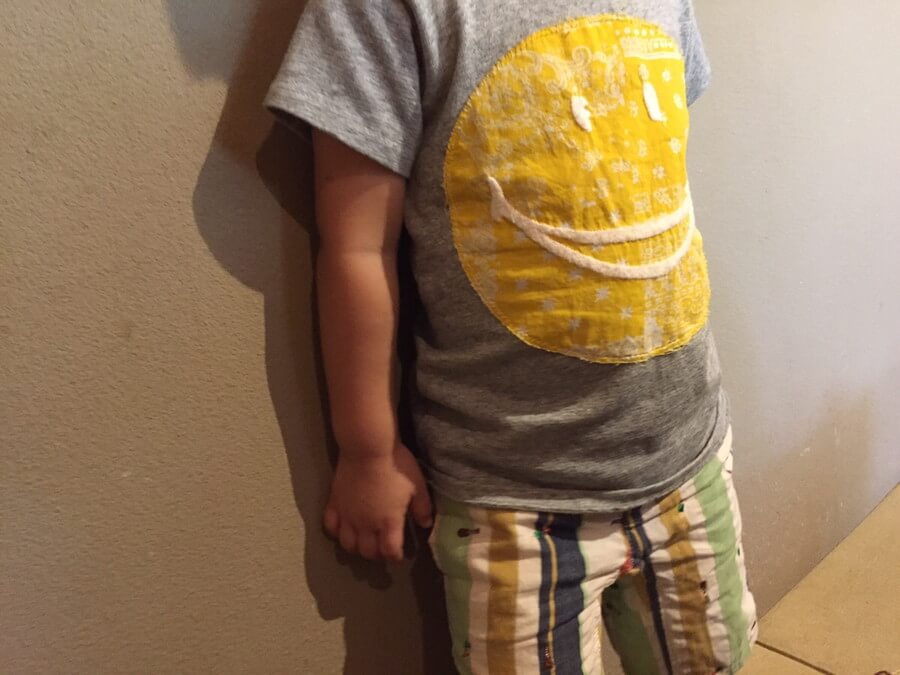子供がお手伝いをしてくれるようになりました!
子供がある程度大きくなって、ちょっとのことであればお手伝いが出来るようになってきたので、遊び心を取り入れつつ片付けの習慣を身につけさせてきたのですが、ついに自発的に子供がお手伝いをしてくれるようになりました!
長い道のりでしたが、小学校になって積極的にお手伝いをしてくれるようになったので本当に有り難いです。
子供を使う、って言い方はおかしいですけど、やっぱり自分の事だけは最低自分で出来るようにさせておかないと、大人になってからもその習慣って身に付いちゃうものですよね。
出来るだけ子供のうちから、出来る事は自分で積極的に行うように誘導して、しつけをしていきたいなぁって思っています。
子供にお手伝いをしてもらうコツ
一番助かっているのが、プリントの仕分けのお手伝いです。
保育園の時にはなかなか自分で仕分けるのは難しかったプリントですが、文字が読めるようになってある程度理解力がついたので、保護者宛のプリントなのか、自分がやらないと行けないプリントなのかが分かるようになりました。
>>頼み方が大切! 子どもが楽しくお手伝いしたくなるコツ
なので帰ってきたらプリント類を仕分けられるようにボックスを購入。
保護者あてのプリントのボックスにプリントを仕分けしたら、そのままダイニングなどに置いておいてもらうように教えました。
そこから宿題があれば宿題をやって、宿題が終わった後、保護者のチェックが必要な物があれば、そのプリントもボックスに入れておいてもらいます。
子供のお菓子の取り出しも、子供に任せるようになったらとっても便利です。
大きめのボックスを用意して、3日分のお菓子+アメヤグミなどの少しずつ食べられるようなお菓子の予備スペース用の、計4ブロックにお菓子を分けたら、子供の手の届くシンクの下などにボックスごと入れておけばOK。
わざわざお菓子を置いておかなくとも、おやつの時間になったら子供が自分で、その日に必要な分だけとっていくので簡単です。
この時、お菓子は基本子供自身に選んでもらって、ボックスに入れるようにしてもらいましょう。
あまりにも偏りがある場合はちょっと組み合わせを変えた方が良いですが、ある程度1ボックスの値段を決めてお子さんが計画的におやつを準備できると、楽しみながら準備を出来ます。
兄弟がいる場合は兄弟それぞれ別の場所に入れておかないと、お菓子が混ざってしまってケンカになる可能性があるので注意です。
こんな風に、ちょっと楽しみながら出来るお手伝いの工夫を取り入れたり、子供でも簡単に出来る工夫をしておくと、子供もお手伝い習慣が身に付きます。
共働きで親が家に居ないときだからこそ、ちょっとした工夫を上手に使いたいものですね。