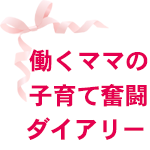今時の子どものスマホ所持率
インターネットが家庭にも普及し始めたのが、2000年代以降です。
それ以降に生まれた子どもたちは、デジタルネイティブ世代と言われることがあります。
学校では一人一台タブレットが貸与され、デジタル教科書による学習や、学校からの連絡事項はタブレットから閲覧するといった動きも出ています。
核家族化や共働き世帯が増え、連絡手段として子どももスマホを持つケースが増えています。
内閣府が発表した「青少年のインターネット利用環境実態調査(令和4年度速報値)」では、10歳で自分専用のスマホの所有は約61%、16歳になると約99%が自分専用のスマホを所有しているという結果が出ています。
小学一年生にあたる7歳の子どもでも、約23%がスマホを所有していることがわかりました。
家庭によって色々な理由を持っているようですが、「登下校の連絡手段」「学校からの諸連絡の受信手段」「コミュニケーションツールの一つ」「携帯ゲーム機のかわり」などがその理由として挙げられます。
何歳からスマホを持たせるかという保護者の悩みもありますが、「一人で学校や習い事などの移動ができるようになったら」「高校生になったら」といったタイミングがスマホを持たせるきっかけになっていることが内閣府の調査結果からもうかがい知ることができます。
スマホを持つメリット・デメリットとは
子どもがスマホを持つことで、親との連絡が取りやすくなります。
GPSなどで子どもの居場所を把握できるのも、保護者からはメリットとなるでしょう。
LINEなどの通話アプリを使えば、家族全員で情報共有ができるのもポイントです。
スマホを持つ子ども自身も、スマホ所有がステータスシンボルとなりますし、友達同士での情報共有もしやすくなります。
一方、スマホを持つことのデメリットも存在します。
動画サイトやオンラインゲームに夢中になりすぎ、勉強などが二の次になってしまうことが親としても一番の悩みとなるでしょう。
また、LINEやインスタグラムなどSNS発信による友人の挙動が気になってしまい、仲間同士のトラブルや対人恐怖などの症状が出てしまうことも挙げられます。
どんな情報でも拡散されるおそれがあるため、何気ない発信が裏目に出てしまうこともあるでしょう。
スマホ決済はもちろん、番号が登録されていればクレジットカード決済なども容易にできるため、ゲームへの課金や通信販売での購入などを親の承諾なしで行うケースもあります。
とくにゲームのアイテム購入は知らずのうちに高額になることが多く、保護者のもとに請求書が届いて事実が明らかになる事がほとんどです。
課金に関しては、スマホ端末とクレジットカードを紐付けないなどの保護者ができる対策を行いましょう。
また、コンビニなどで電子マネーカードを購入することに関しても家族で話し合う時間を設けましょう。