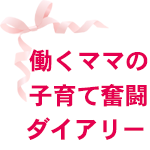親もこどもも楽しい運動会にするには
運動会ではこどもの活躍に涙してしまう親御さんも少なくないですよね。まだまだ最近歩けるようになった子たちが頑張って踊っている姿は他人のこどもでも感動してしまいます。イベントに注力してしまうあまり、こどもに厳しく当たってしまう家庭もあるようですが、運動会はこどものイベントです。親がアレコレ口出しするのはこどものやる気をそいでしまいますので注意してくださいね!
こどもたちが主役の運動会をより楽しいイベントにするために私たちができることをご紹介します。
親子ともども楽しめるように是非試してみてください!
かけっこの練習
幼児でも小学生でも一番ワクワクするのがかけっこですよね。一番になれたら嬉しいですが、早く走るためには練習が必要です。
スパルタにやり過ぎてしまうとこどもはモチベーションを落としてしまうかもしれませんので、一緒に楽しみながら練習していきましょう。
幼児の場合は、ちょっとしたことだけで早く走れるようになりますし、小学生でかけっこが苦手な子でもコツを掴んだら突然早くなる子もいます。保育園や小学校で練習が始まったら、家庭でも少しずつ練習を取り入れてみてはいかがでしょうか?
始めるタイミング
小学生くらいのこどもは幼児のかけっこより距離が長いこともあり、体力を付けることから始める必要があります。すぐに体力は付かないので、運動会本番の1~2か月前から練習するのがベストです。
早く始めすぎて練習量が増えてくるとこどもは飽きてしまうこともあります。ワクワクしながら、早く走れるようになるちょうどいいタイミングが1~2か月としていますが、こどもによっては1か月未満で飽きてしまったり2か月では間に合わなかったりするこどももいるかもしれません。一番近くで見ているご家族がこどもの性格や運動神経に合わせて調整してあげてくださいね!
最初は走る以外に縄跳びをしたり、追いかけっこのような遊びで体力を付けていったりしていきましょう。縄跳びはバランス感覚も良くなるので、体の筋肉を作るのにも適していますよ。こどもから「かけっこで早く走れるようになりたい」と言われてからでも遅くはありません。
こどものやる気に合わせて始める方が楽しみながら練習できますよ。
靴の見直し
小さいこどもだとマジックテープタイプの靴を使っている子が多いと思います。実はこのテープタイプのシューズをきつめに締めるだけでも早く走れるようになります。
足のサイズにピッタリの靴はまだ選ぶのが難しいので、少し大きめのサイズになっていることがあります。こどもでも履いたり脱いだりしやすいように簡単に外れるテープ状になっているので、ギュッときつめに締めるだけで靴の中で足が動かなくなり、走りやすくなります。
運動会で靴が脱げてしまったら練習の成果を出せません。練習するときから走る前にはギュッと締めることを教えてあげましょう。
幼稚園や保育園では裸足でかけっこをする場合もあります。その場合は、爪切りのしすぎに注意です!
爪を切り過ぎると痛みやすいのもありますが、力が入りにくくなってしまうこともあります。ただ逆に伸びすぎているのもNGです。
隣の指に爪が刺さってしまうような長い爪は危ないですし、裸足でのかけっこ練習のときに割れてしまうこともあります。
ですが、伸びすぎているとき以外は本番直前に切るのは避けてくださいね。一週間前に切っておくと足と爪も馴染んでくるので直前ではなく、少し前から準備しておきましょう。
フォームを教える
つい最近走れるようになったこどものフォームはむちゃくちゃです。
ブンブン手を振り回して、足はペンギンみたいにパタパタしている姿もかわいいですが、このフォームを直すだけでも早く走れるようになります。
コツは手の指先と腕です。手を小さく前ならえの状態にさせ、指先はグーとパーの間くらいに曲げて怪獣の手のような形にします。
グーにしない理由は力が入り過ぎてしまうためなので、怪獣の手でも力は入れすぎないようにしてください。
肘を90度に曲げた状態で腕を縦に振らせるのですが、肘が曲げたり伸ばしたりしてしまいます。これでは力が分散してしまうので、肘を固定したまま腕を前後に動かすようにしていきましょう。風船を顔の前にぶら下げ、下から上に逆チョップするような感じで練習すると楽しめますよ。
肘のうしろにも風船をぶら下げて、肘が当たるように引けるようになると腕のフォームはOKです!
スタートとゴールの意識
こどもたちはスタートの合図と同時に動くことがとても難しいです。よーいドンの掛け声があってから走り出しては一番になるのが厳しいため、家で練習するときはスタートダッシュの練習を一番多くするといいでしょう。
スタートの練習では「位置についてよーいドン!」という掛け声と、「よーいドン!」の短縮型、少しためて「よーい…ドン!」、早口の「よーいドン!」など複数パターンで練習しましょう。小学校低学年くらいまでは走る速さにほとんど差がないため、スタートダッシュができるだけで一番になる可能性が上がります。「ドン!」のタイミングで手を叩いたり太鼓を使って大きな音を出したりするのもポイント。音にビックリして走り出しが遅れたりするのを抑える練習です。
耳だけでなく、指示する先生をしっかり見るようにするのもコツです。こどもは手の動きで、来るぞ来るぞ…と構えておくことができます。
音や声を出さずに手だけで走り始める練習をしてみるのもいいかもしれません。
また、ゴールの意識も大事です。
ゴールテープを切るのを目標にしてしまうと失速してしまうため、テープを振り切って走り抜ける気持ちで練習してください。
小さいこどもだと、テープを掴んだらお母さんに届ける気持ちで走ってね!というだけでゴールを走り抜けてくれますよ。
幼児のお遊戯・ダンス練習
運動会の出し物でダンスやお遊戯をするところもありますよね。
上手に踊ってほしい!という親の気持ちもありますが、こどもにとってお遊戯やダンスはとても難しいことなのです。
練習をたくさんしても、当日緊張してしまったら体がカチカチに固まってしまって動けないということもあります。
幼稚園や低学年のダンスの振り付けはネットに上がっている振り付けが多いので、家でもみながら練習できる曲もあるので、担任の先生に聞いてみるのがおすすめです。
お遊戯やダンスはハードルが高い
大人には単純なことでも、こどもにとってはとても難しいダンス。音楽を聞いて、手と足を別々に動かして、音楽に合わせて、お友達との距離感や配置にも気を付けながら言われた通りの振り付けで体を動かす。一つひとつバラバラの作業にしたらかなりのマルチタスクです。
振り付けは簡単に見えて、こどもたちにとってはとても大変な作業なので、すぐにできなくても仕方ありません。
ダンスが苦手な子には、手遊び歌から始めるのが「グーちょきパーでなにつくろう」の歌や「とんとんとんとんヒゲじいさん」の歌で、まずは歌いながら手を動かすことをしてみてください。上手にできる子は、立った状態で歌に合わせ行進してみるとか、ジャンプしながらやってみるとか、増やしていきましょう。音楽に合わせて自分の手と足を動かせるところまでできるようになれば、言われた通りの振り付けや、周りの人にぶつからないようにするということに気を向けられるようになります。
振り付けを楽しめることが第一ですが、自分の好きな独創的な振りに変えてもいいのです。こどもが楽しく踊っているなら、一緒に同じ振り付けで踊ってみてください。すると、こどもは「もっとこうだよ」とか「もっとこんな風にして」と指導してくれます。言われた通りに直しながら、「次はお母さんが振り付けするから一緒にやってみよう!」と本来の振り付けに戻すとすんなりできるようになったりもするものです。
あーして!こーして!とガミガミしてしまうと楽しくなくなってしまいますが、一緒に楽しみながら覚えていけば、本番硬直してしまうことも少なくなるかもしれません。
練習での注意点
否定をしないことと、笑わないことです。
振り付けが間違っていても「違う」とか「そうじゃない」とか口出ししないことが大事。否定されると気持ちよくないのは大人もこどもも一緒です。
できるだけ肯定してあげて、ポジティブな形で訂正するようにしましょう。
また、本人は真剣にやっているのに笑われたらとても悲しくなってしまいます。不格好でも笑ったりせず、お調子に乗って変なポーズしていても笑ったりせずにいることがポイントです。楽しくやるのが大事ですが、変なところで笑ってしまうと、ウケたことに満足感を覚えて、変なポーズばかりしてしまうかもしれません。
幼児も低学年もストレスになる
ダンスやお遊戯は、自分のやりたいように動き回れなかったり、好きなことができなかったり、こどもにとってはストレスが溜まりやすいことです。
家に変えるとグズリ気味だったり甘え気味だったり、イライラしてしまうこどもは少なくありません。
保育園や学校で練習が始まってからの体調の変化や気分の起伏などは親がしっかり把握して、ストレス過多になっていないか気を付けてあげましょう。好きじゃない子にとっては苦痛でしかないので、家では無理に強要せず、甘えさせてあげて、ォローもしっかりしてあげてくださいね。
やっぱり最後は褒めて伸ばす!
小さいこどもだけでなく、小学生に上がっても褒めて伸びる子はたくさんいます。
幼児には「○○くんカッコいいね!△△のようにしたらヒーローみたいにもっとカッコよくなるね!」とか、「昨日も練習たくさん頑張ったからとっても早くなってる!すごいね!」と褒めるとやる気やモチベーションがアップすることもあります。
少し恥ずかしがる年齢には「昨年の○○ちゃんカッコよかったから今年も楽しみにしてるね!」「諦めずに練習してきたからきっと大丈夫!」とか背中を押すような励ましの言葉がモチベーションアップにつながります。
親子で楽しい運動会にするためにも、事前準備とサポートに取り組んでみてくださいね!