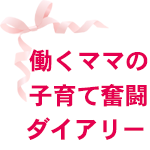子どものわがままに思わずイライラ
ワーキングママたちは、仕事をするほか家事や育児を担うなど、さまざまな顔を持ち合わせています。
なかでも「母親」役割を担っているときは、一番負担に思うのではないでしょうか。
「あれイヤ」「これじゃダメ」「え~なんで?」「違う!」など、否定する言葉ばかりでママを攻めてくるのはイヤイヤ期の子どもだけではありません。
思春期に差し掛かった子どもでも、わがままとしか取れない要望を重ねて来ることがあります。
わがままとは、相手や周りのことを考えずに自分の主張を通そうとすることや、自分自身の思い通りにならない場合に怒りを表すさまを差しています。
幼い子供のイヤイヤ期や思春期の反抗期は一過性のものであり、時間とともに大人になると言われています。
子ども自身も「わがままである」ことは漠然とわかっており、親がたしなめることである程度は理解を示します。
しかし、仕事や家事に追われて毎日くたくたになっているママからすれば、わかっていてもイライラしてしまうものですよね。
子供に怒鳴っても仕方がないのに、イライラが爆発してつい怒鳴り声をあげてしまう悪循環が生まれ、自己嫌悪に陥ってしまいます。
子どものわがままの対処法は?
子どものわがままは、親への甘えや自分の存在をアピールするために引き起こされる事がほどんどです。
また、幼さ故に自分の気持ちを言い表せないケースや、相手や身の回りへの配慮ができないこともその理由として挙げられます。
気持ちを言葉にできないケースは未就学児頃までのわがままのケースですが、親に甘えるためのわがままや、自分の存在を一番に扱ってほしいために繰り広げられるわがままは年齢が高くなるほど顕著になります。
年齢が低い子どものわがままの場合、親がその気持ちを受け止め代弁することで落ち着きます。
「眠かったんだね」「もう少し遊んでいたかったね」というように、気持ちを受けた止めた上で「こういうことはダメなんだよ」と丁寧に伝えることが大切です。
言葉による意思疎通ができる子どもなら「どうしたかった、何がしたかった」というような子どもの話を聞いてください。
言葉を引き出したら、まずは否定や説得をせず子どもの気持ちを受け止めましょう。
頭ごなしに叱ることや、げんこつなどの体罰でわがままを止めるのは良いことではありません。
子どもの気持ちを尊重しながら「我慢すること」「他人の気持ちを考えること」を根気強く教えていきましょう。
わがままの対処法は、育児書などでもさまざまな手法が掲載されています。
それぞれ表現が異なりますが、子どもの話を聞く、言葉で諭すという方法は基本的に変わりません。
このベースがうまく構築されると、思春期の子どもとのコミュニケーションもうまく行きますよ。